◇理科の教育が難しいといわれています。
2007年度から小学校に,理科実験助手が入っています。
さらに,この年には,日本学術会議が,理科教育において教員の資質向上が必要だという要望書を,文部科学省に提出しました。
◇理科の授業は本来楽しいものです。 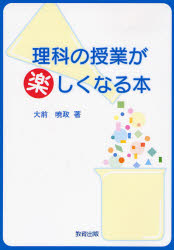
しかし,小学校の教師の多くが,理科が苦手と答えているアンケート調査結果があります。
(科学技術振興機構2005年の調査では,62%の教員が理科が苦手と答えています。)
◇楽しい授業はどうすればできるのか。
「教師が理科を楽しむことが大切だ」,などとよく(大学で)言われますが,これは解決にはなっていません。
やはり楽しい理科授業には,それなりの方法があるのです。
◇本書に,理科の授業を楽しくする手立てを紹介しました。
小学校や中学校,高校で理科を教えている先生や,理科研究室の学生に是非読んでもらいたい本です。
また,塾などで理科を教えている先生にも役立つことでしょう。
地域で,「理科教室」などをしている人にも是非おすすめします。
◇目次
1 子どもが理科を好きになる
(1)観察の方法を工夫するだけで授業が激変する
(2)授業の組み立てで子どもが熱中する
(3)討論で授業が盛り上がる「4年もののかさと温度」
(4)授業の最初にインパクトを
(5)実物に触れるから興味がわく
(6)知的理科クイズで授業に変化を
(7)子どもの認識の誤差から授業は発展する
(8)単元の最初からたっぷり実験する
2 理科の授業の基礎技術
(1)理科の授業の型を使い分ける
(2)教科書通りの実験の進め方
(3)実験ノートは正確かつ美しく
(4)観察記録のとらせ方の原則
(5)特別支援教育に対応する
3 確かな学力を保証する
(1)知識と実感を結びつける
(2)学習した知識を出力する場面を設定する
(3)ノートまとめは美しく
(4)技能は繰り返して身に付けさせる
(5)中学年の理科授業開き
(6)高学年の理科授業開き
4 科学的思考力を伸ばす
(1)探究型理科授業を提案する「6年電流のはたらき」
(2)実験の連続で素朴概念から科学的な知識まで高める 「6年ものの燃えかたと空気」
(3)条件の統一ができるまでにも指導がいる
(4)結果から結論を考察する力を養う
(5)本当にわかるまで追究させる
5 おもしろエピソードを語る発展学習
(1)親指ってすごいな!拇指対向性から進化を知る
(2)ピュアウォーターの大切さを知る
(3)最先端の科学を授業する「脳科学」の授業
(4)環境問題を授業する「ネットワーク思考」の授業
◇本書の特長は,なんといっても,「子どもを理科好きにするための手立て」が,理科の全領域にわたって示されていることです。
******************************
理科を教えるための,教え方の工夫と,良質のネタが紹介されている。
******************************
子どもを理科好きにできるかどうかは,教師のチカラ次第です。
大学で学ばなかった,「理科の教え方」を,是非この機会に知って欲しいと願っています。
|

