◇理科の授業をしていると,とても楽しいです。
子どもたちも楽しいと言います。
ただし,これは,理科の授業の進め方をきちんと学んで知っている場合です。
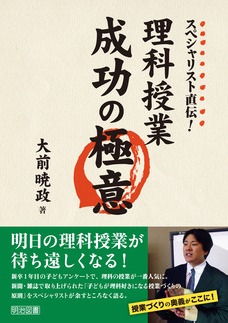
◇例えば,次のような問いに答えられるでしょうか。
************************
「理科の授業において,最初に何をしますか。」
************************
理科の授業の導入で最初に何をしたらよいのでしょうか。
こんなことすら,教えられていないと答えられません。
◇もっと基礎のことをで,次のことに答えられるでしょうか。
*****************************
発問で気を付けたらいいことは何ですか。三つ答えてください。
*****************************
これも,学生さんなんかに聞くと,バラバラの答えが返ってきます。
つまり,教わっていないのです。
だから,あてずっぽうでしか答えられないのです。
これでは,まずいです。
先人の実践や現在の教室で行われている新しい「技術」や「方法」を学ぶ必要があります。
このような基本的な「授業づくり」の方法をこそ,知る必要があります。
◇学力重視の影響を受け,理科の教科書が分厚くなっています。
今までの教科書とは,質も量も変わっています。
授業の時数も増えています。
今後も,学力重視の方向性は変わらないことが,文部科学省から発表されました。
多くの学習内容を,きちんと教えようと思ったら,やはり教師自身が,学ばなくてはなりません。
理科の授業を得意になろうと思ったら,まずは,基礎となる「授業づくりの方法」を知ることなのです。
理論を知ることではありません。
具体的な,やり方,方法を知ることが必要なのです。
◇私の理科の書は,大きく三つのジャンルに分かれています。
***************
①授業づくりの本
②授業技術の本
③授業の1年間の全記録
***************
「理科の授業が楽しくなる本」(教育出版)は,「授業づくり」の本。
「なぜクラスじゅうが理科を好きなのか」(教育出版)のシリーズは,「授業の1年間の全記録」。
「たいくつな理科授業から脱出する本」(教育出版)が,「授業技術」の本です。
そして,本書「スペシャリスト直伝!理科授業成功の極意」は,これまでの理科論文を集めたものとなっています。
いわば,上の三つの要素全てを,あわせもった書籍となっているのです。
理科が専門ではない人も。
理科が得意な人も。
理科について学びたい人の,とりあえずの最初の一冊に最適の本となるでしょう。
|

